
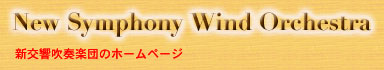

|
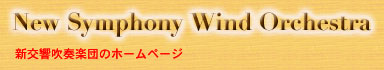
|








|
|
|||||||||||||||||||||||
| 創立40周年記念演奏会(第58回定期演奏会) | |
|---|---|
| 日時 | 2001年10月5日 |
| 会場 | 東京文化会館・大ホール |
| 客演指揮 | 井?正浩 |
| ピアノ | 寺嶋陸也 |
| 曲目 |
 バレエ組曲「火の鳥」(1919年版) ★ I.ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版) ★ I.ストラヴィンスキー ラプソディ・イン・ブルー ★ G.ガーシュイン (ピアノ独奏:寺嶋陸也) ラプソディ・イン・ブルー ★ G.ガーシュイン (ピアノ独奏:寺嶋陸也) 幻想交響曲 ★ H.ベルリオーズ 幻想交響曲 ★ H.ベルリオーズ 亜麻色の髪の乙女 ★ C.ドビュッシー(アンコール) 亜麻色の髪の乙女 ★ C.ドビュッシー(アンコール) 「アルルの女」第2組曲から「ファランドール」 ★ G.ビゼー(アンコール) 「アルルの女」第2組曲から「ファランドール」 ★ G.ビゼー(アンコール)
|
| 来場者数 | 2141 |
| 演奏会プログラムにお寄せいただいたメッセージを掲載いたします |
|---|
|
今回の新交響吹奏楽団との共演は、私にとっては3つの楽しみがありました。 ひとつめは、久しぶりのブラスの指揮であることです。福岡から上京して師の門を叩いた時、初めて指揮の機会を与えていただいたのはオーケストラでなく、ブラスバンドでした。まだ基礎的な指揮法を学んでいた時でしたが、実際に指揮をするということは、教わったメソードを実践するというだけでなく、自分流の演奏スタイルや指導法を確立するための格好の”現場”でした。その時に体にしみこんだスタイルというのは、今でも私にとってのスタンダードなのです。今回の演奏会のためのリハーサルで、私は原点に立ち返ってブラスによる音楽作りに専心したのでした。 ふたつめは、ブラスによる音楽の可能性を広げる試みにチャレンジできることでした。今回のプログラムである「火の鳥」「ラプソディ・イン・ブルー」「幻想交響曲」というのは、いうまでもなくオーケストラのために書かれた曲です。しかし今回管弦楽でなく吹奏楽で演奏することによって、これらの曲に新しい光を当てたいと思いました。それはオーケストラの曲を単にブラスバンドに移し変えるという作業でなく、新たな曲として再創造するという域にまで高めたいという欲求から起こったものです。その私の試みに、この新交響吹奏楽団は見事に応えてくれました。 みっつめは、この楽団を指揮できるという喜びです。今回この演奏会の指揮のお話しを頂いた時に、その後すぐに行われたこの楽団の演奏会を聴くことが出来ました。自分たちの専属のアレンジャーと指揮者を持ち演奏するこの団は(まさに楽団の特徴を生かした音楽作りが出来ることでもあり)魅力的なサウンドと、奇をてらわないがっちりとした音楽作りが出来る団だとその時確信しました。そして演奏しているメンバーの表情を見て、きっと一緒に音楽を作り上げる喜びを味わえるだろうと思ったからです。 音楽のジャンルには様々なものがあり、その表現媒体も多岐にわたります。今日の演奏会では、前述の私の三つの楽しみをお聴きになっているお客様と共有出来ればうれしいと思っているのですが、特にクラッシックだ、ブラスバンドだ、という枠を少しでも超えて、新交響吹奏楽団のサウンドに感じる『音楽の心地良さ』や『音楽を表現する喜び』をぜひ伝えたいと思っています。どうか、ごゆっくりお楽しみください! |
| 指揮・井?正浩 |
|---|
 '95年5月の"ヤーノシュ・フェレンチク記念"ハンガリー国営放送主催・第8回国際指揮者コンクール(ブダペスト国際指揮者コンクール)優勝以来、国内外にわたって目覚ましい活躍をしている指揮者。
'95年5月の"ヤーノシュ・フェレンチク記念"ハンガリー国営放送主催・第8回国際指揮者コンクール(ブダペスト国際指揮者コンクール)優勝以来、国内外にわたって目覚ましい活躍をしている指揮者。国内では '96年1月に東京シティーフィルのニューイヤーコンサートを指揮してデビューを飾って以来、同楽団をはじめ読売日響、日本フィル、九響、群響、神奈川フィルなどのオーケストラを次々と指揮し、「パワーとエネルギーを十分に保持し、しかも細かいところをかっちりと揃えた音楽作り」(音楽芸術)「明確な表現意図を持ってメリハリの効いた、凝縮力のある演奏」(音楽舞踏新聞)など高い評価を受けている。 海外では、特にその拠点をハンガリーにおき、これまでにハンガリー国立交響楽団、ブダペスト交響楽団、ハンガリー国立歌劇場管弦楽団(ブダペスト・フィル)、セゲド交響楽団等をハンガリーの主要オーケストラをほとんど指揮し、「ヨーロッパの精神を持った指揮者」(マジャール・ヒールラップ紙)などの高い評価を得ている。また特筆すべきは、コンクール中の演奏を認められ、ハンガリー国立ブダペスト・オペレッタ劇場に招かれレハール作曲「メリー・ウィドゥ」を指揮してデビュー、その後'96年1月の同劇場初の日本公演にも指揮者の一人として同行し成功に導き、その手腕を絶賛され、「音楽の友」誌の特集「コンサート・ベストテン'96」にも選ばれ、'97年6月及び'98年1月の同劇場の再来日公演でも各誌より称賛を浴びており、「日本人離れした才能と感覚」(読売新聞)との評価を得ている。'98年1月には国内で初のライヴCD「メリー・ウィドゥ」(ムジークレーベン社)が発売された。 またこれまでのハンガリー国内での演奏のほとんどが国営テレビ・ラジオで中継あるいは放送され、ハンガリーで最も良く知られた日本人の一人となっている。'98年9月からはハンガリー西部のソムバトヘイ市を本拠とするサヴァリア交響楽団の芸術監督、常任指揮者への就任し、同国内で精力的に活動している。その他ドイツ、スイス、ルーマニア、イスラエル、韓国等において多くのオーケストラや劇場でのオペラ指揮へのデビューを控え、これからの活躍に目の離せない指揮者である。 指揮法を安永武一郎、故カール・エスターライヒャー、ギュンター・トイリング、湯浅勇治、遠藤雅古、伊藤栄一の各氏に師事。福岡教育大学卒業、東京学芸大学大学院修了、オーストリア国立ウィーン音楽大学に留学。アマチュアの指導にも力を入れており、リコーフィルハーモニーオーケストラの常任指揮者を務めて今年で12年目となるほか、新交響楽団、熊本交響楽団、トヨタ青少年オーケストラ・キャンプ(TYOC)などの団体も指揮している。 (リコーフィルハーモニーのWebページより転載の上、一部修正・加筆。) |
| ピアノ独奏・寺嶋陸也 |
|---|
 1964年東京生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科に入学、92年同大学院修士課程修了。在学中から作曲とピアノ演奏の両面で積極的に活動を行い、特にオペラシアターこんにゃく座をはじめとする劇場での演奏は高く評価された。
1964年東京生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科に入学、92年同大学院修士課程修了。在学中から作曲とピアノ演奏の両面で積極的に活動を行い、特にオペラシアターこんにゃく座をはじめとする劇場での演奏は高く評価された。86年、第1回摂津市音楽祭L.C.コンクールのピアノ演奏で金賞受賞。89年、東急Bunkamuraシアターコクーンのオープニング公演ホフマン物語」では音楽監督をつとめた。93年から95年まで、グリーンホール相模大野でコンサートシリーズ「20世紀の古典」を企画・構成。 95年、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の委嘱により『尺八・二十絃箏と管弦楽のための協奏曲』を、また北九州市の響ホールフェスティヴァルの委嘱により『弦楽四重奏曲第三番』を作曲。97年、東京都現代美術館「ポンピドー・コレクション展」開催記念として開かれたサティ連続コンサート伝統の変装」(全6回)を構成・出演し好評を博す。98年、オックスフォード大学モードリン・カレッジ聖歌隊の委嘱で『詩編第49番』を作曲。作曲のほか、室内楽を中心とするピアノの演奏やコンサートの企画、99年からは北海道美幌町の「子どものための美幌国際芸術祭」の音楽監督に就くなど、活動は多方面にわたっている。 作品には、ほかにオペラ『ガリレイの生涯』、混声合唱のための『オレンジの木かげ』(G.ロルカ詩)、『みち』(谷川俊太郎詩)、ピアノのための『12の前奏曲』、『無伴奏ヴィオラ・ソナタ』、オーボエ・三味線・打楽器のための『異郷の景色』などがあり、近作には国立劇場の委嘱による正倉院の復元楽器のための『大陸・半島・島』をはじめ邦楽器のための作品も多い。 ソロCDに、シベリウス、スヴェーリンク、シューマンと自作を収めた「ディオニュソスの子供達・第三章・寺嶋陸也」(DIONYSIA)、その他室内楽や歌曲の伴奏など、多くのCDがある (寺嶋陸也氏による) |
| HOME > 演奏会情報 > 2001-2005 > 第58回定期演奏会 |